内定先:アクセンチュア株式会社/ソリューション・エンジニア
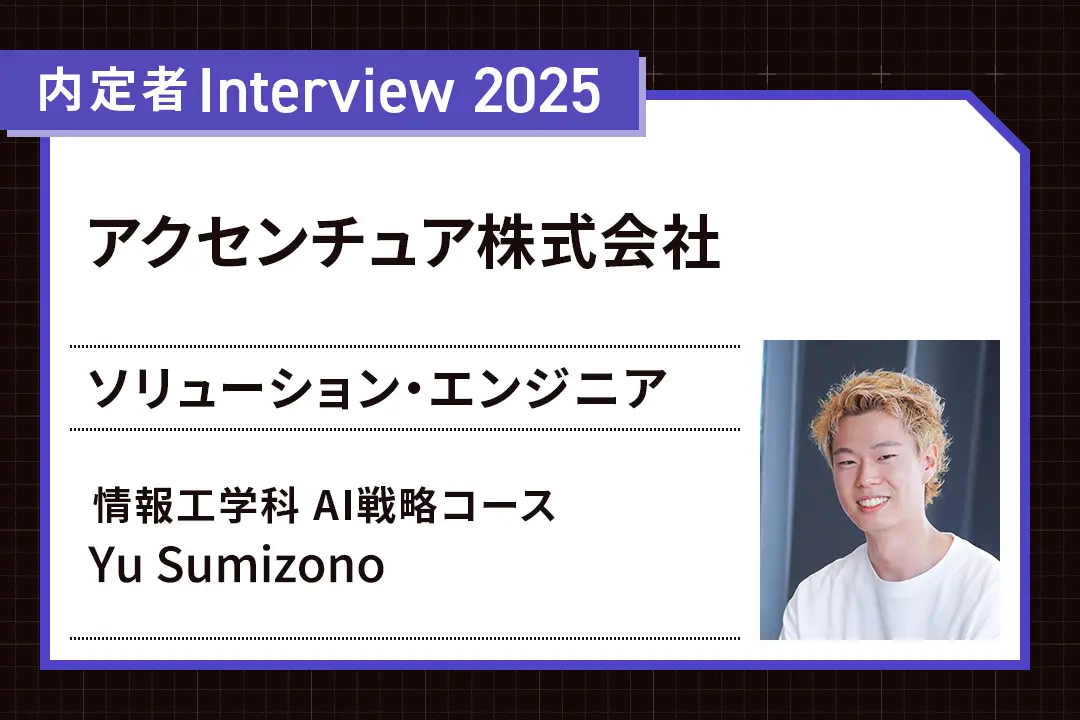
■内定先
アクセンチュア株式会社
デジタルの力で企業や公的機関の変革を支える、世界最大級のコンサルティング企業。 ITに強みを持ち、戦略策定から業務改革・実行まで多くの業界の様々な業務領域を網羅。
■配属先・職種等
ソリューション・エンジニア
AI×実践力で未来を切り拓く。IT初心者から、大学で身につけた3つの確かな力
・実践的なカリキュラムから、「社会に出てすぐに活躍できる力が身につく」と確信し、入学
・将来につながる3つの力(実践的なITスキル、ソフトスキルの向上、GRIT・やり抜く力)を得られた4年間
・就職活動はキャリアサポートセンターの支援あってこそ。希望通りの嬉しい内定へ!
本学への入学について
Q. 本学を知ったきっかけと、入学の決め手を教えてください。
高校時代、進路に迷っていたときに大学情報サイトで知りました。PepperやSiriなどのAI技術にも触れる中で、ITや人工知能への興味が深まり、実践力を重視する本学のカリキュラムに魅力を感じました。
個別相談会に何度も参加することで、設立直後という不安も払拭され、「社会に出てすぐに活躍できる力が身につく」と確信。英語教育にも力を入れている点も、将来的にグローバルなフィールドで活躍したい私にとって大きな魅力でした。
Q. 学科・コースを選んだ理由を教えてください。
人工知能への関心が出発点です。高校時代、身近なAIに触れる中で、「なぜ人間の言葉を理解できるのか」「どうやって会話が成立しているのか」といった疑問から、技術の裏側に強い興味を抱くようになりました。
AIを本格的に学ぶためには、その基盤となる情報工学の知識が不可欠だと知りました。
AIはただの一つの技術領域ではなく、プログラミング、アルゴリズム、データベース、ネットワークといった広範な情報工学の土台の上に成り立っている、だからこそ、まずは情報工学全体をしっかりと学び、土台を築いたうえで、将来的により専門的なAIの分野へと進みたい、と考えるようになったのです。
加えて、この学科では理論だけでなく、実習を通じて実践的に学べる点にも大きな魅力を感じました。知識を使える形で身につけることで、より深い理解と応用力が得られると考え、情報工学科への進学を決意しました。
Q. 入試はどうでしたか?
総合型選抜を受験しました。
パンフレットなどに「すべての受験者の意欲、情熱と熱意を評価します。」と明記されていたため、学力の一点突破ではなく、自分の熱意や考え方そのものが問われる入試だと感じ、志望理由書と面接対策に特に力を入れました。
志望理由書では、なぜこの大学で学びたいのかを自分の体験に基づいて論理的に組み立て、読み手に納得感を与えられるように意識。単なる「好きだから」ではなく、「なぜ好きなのか」「どのような背景があるのか」「将来どう活かしたいのか」といった流れを明確にしました。
当日はペーパーテストもあり、記述式の問題では、自分の考えをしっかりと表現できているか少し不安を感じた部分も。しかし、その後の面接では「正解を答える場」ではなく、「自分という人間を理解してもらう場」だと考え、暗記した回答を繰り返すのではなく、自分の考えの軸をしっかり持って話すことを大切にしました。コミュニケーションとしての面接を意識することで、自分の言葉で伝えることができたと思います。
全てを終えて振り返ると、この入試は、単に受験時点での学力や能力を測るだけでなく、「しっかりと志があるのか」「自分が何をしたいのか」という、個人の内面まで深く見極めようとするものだったと感じます。私の「やる気」と「志」が評価された結果だと思っています。
カリキュラム・学びについて
Q. 本学で学んで良かったことや成長したこと、印象に残っていることは?
大学生活で得たものは、これからのキャリアを力強く支える確かな財産だと感じています。特に3つの力を身につけることができました。
① 実践的なITスキル
ITスキルを単なる知識としてではなく、「実践的な力」として身につけられました。ITの知識やプログラミング能力を身につける上で、論理的な思考力やシステムの構成を理解することは非常に重要。しかし、それだけでは実社会では通用しません。なぜなら、実際にITが使われる現場では、机上の理論だけでは解決できない複雑な要因が絡み合うからです。この大学での学びを通じて、私はその「現実」を肌で実感。4年間で合計約600時間にも及ぶ実践的な実習は、まさにその最たる例です。現場での経験を通して「学んだ知識」を「使える知識」へと昇華させることができたのは、何よりも大きな収穫だった。
また、実習を通じて早い段階からIT業務の現場を知ることで、他大学の学生よりも深いIT業務への理解を進められたと自負しています。これにより、入社後に「想定していた業務と違う」といったミスマッチが生じる可能性も限りなく低いと考えます。実践的な学びがあったからこそ、私は自信を持って新たなフィールドへ踏み出せるのです。
② ソフトスキルの向上
ソフトスキル、すなわち「人としての土台」を鍛えられました。
専門的なIT知識と同様に、ビジネスパーソンとして、そして一人の人間として不可欠なのが、コミュニケーション能力やリーダーシップ、チームワークといったソフトスキル。これらは、あらゆる専門知識の土台となる個人の習慣や特性と言えると思います。
本学では、数多くのグループワークに取り組む機会に恵まれました。そこでは、個人の能力だけでなく、グループ全体としての成果を出すことが常に求められます。高い成果を追求する過程では、単に専門知識があるだけでは不十分です。他者の考えを深く読み取り、理解する力、そしてグループメンバーと円滑なコミュニケーションを取りながら、時にはリーダーシップを発揮し、相手に分かりやすく伝える力が非常に重要になります。
4年間、様々な仲間と関わりながら、実践を通してこれらのソフトスキルを磨き上げることができたのは、私の大きな強みとなりました。この経験は、入社後にチームの一員として働く上で、間違いなく私の推進力となると感じます。
③ グリット(やり抜く力)
私が最も重要だと考えているのが、グリット(GRIT:やり抜く力)を培うことができた点です。グリットは、以下の4つの要素から成り立ちます。
- 1. Guts(度胸): 困難なことに臆することなく立ち向かう勇気
- 2. Resilience(復元力): 失敗しても諦めずに、粘り強く続ける力
- 3. Initiative(自発性): 自分で目標を見据え、積極的に行動する力
- 4. Tenacity(執念): 困難な状況でも最後までやり遂げる執念
この大学には自発的に行動し、成長できるチャンスが数多くあります。私は日々の課題に取り組む際も、そして実習先を選ぶ際も、常に「より難しい道」を選ぶように意識。与えられた要件に自分なりのアイデアをプラスしたり、新たな知識を習得するためにあえて難易度の高い実習先を選択したりと、常に向上心を持って挑戦を続けてきました。この「やり抜く力」は、自然と身につくものではなく、自ら積極的に行動し、困難に立ち向かって初めて手に入れるチャンスが生まれます。
この大学は、ただ通うだけではなく自ら行動し続けることで、確実に自分を変えてくれる場所。今後この大学を志す人、在学中の人には、自分の可能性を信じて、挑戦することを恐れないでほしいと思います。

Q. 産学連携の実習や、企業インターンシップ「臨地実務実習」はどうでしたか?
実習カリキュラムは多岐にわたり、社会に出る上で必要な実践的な力を養う貴重な機会でした。
・「地域共創デザイン実習」(2年次)
学科の垣根を越えてグループを組む実習です。私は株式会社セガ エックスディーで「学生目線の社会課題の発見」をテーマに実習を行いました。日頃から解決したいと考えている課題に対し、「なぜ解決したいのか」「それが課題の本質なのか」を常に問い続けながら議論を重ねました。この実習で、企業のCOOの方から直接アドバイスをいただき、ビジネスを体感できたのは非常に貴重な機会でした。メモの取り方一つとっても、学びとなる点が多かったことを覚えています。
・「ソリューション開発Ⅰ,Ⅱ」(3~4年次)
企業との産学連携の中で、位置情報を用いた地域課題解決プラットフォームの構築に取り組みました。
この実習では、与えられた課題をこなすのではなく、自分たちで課題選定から企画、開発までを一貫して実施。少人数のグループで開発を進めるため、実装力はもちろんのこと、1年間のプロジェクト計画力も求められました。この実習を通じて、実際のプロジェクトにおける進捗管理や、開発の一連の流れを体験できたのは大きな収穫です。チームマネジメント力がプロジェクト成功の一つの要因であることを肌で感じることもできました。
・「臨地実務実習Ⅰ」(2年次)
企業へインターンシップに行き、AI関連の興味のある技術について研究するという内容で、私は幾何学問題を解く生成AIに関する研究を行いました。この実習を通して、私は研究者としての道ではなく、技術を使って具体的な価値を社会に届けたいのだと、自身の将来の方向性を考えるきっかけを得られました。
このように、多様な実習を体験することで、将来何をしたいのか、どんなことに興味があるのかを模索できるのが、本学のカリキュラムの大きな強みだと考えます。様々な業務内容を体験できることで、自己理解が深まるのです。
・「臨地実務実習Ⅱ」(3年次)
就職活動の時期と重なり、より本格的に自身の将来を見据えながらの実習になりました。
大手デジタルコンテンツ企業でのインターンシップで、企業の課題に取り組みました。自分が持っている知識だけでは足りない部分も多く、自ら情報をキャッチアップして分析する力が強く求められ、自らのモチベーションコントロールも重要であることを痛感しました。
・「臨地実務実習Ⅲ」(4年次)
就職後の自分のためのスキルアップも意識した企業インターンシップになり、主にソフトスキルの向上に取り組みました。今やAIを活用すれば議事録も録音から自動で生成できる時代ですが、会議の中で何を話し合ったのか、決定項目は何なのかを自分の言葉でまとめ、他者が読んでも分かりやすく整理する力は非常に重要です。議事録作成能力やプレゼンテーション能力の向上を目標に実習を行い、社会人としてのスタートダッシュに備える機会となりました。
・「人工知能応用」(3年後期)
AI戦略コースの授業で、自分でAIシステムを構築し、それを多くの企業の前でプレゼンテーションする内容でした。システム構築中は疑問点を自ら調べ、教授や友人と協力しながら解決していきます。論理的に企業の方にプレゼンする力をはじめ、様々な力を駆使しながらこの講義を乗り越えました。学生の中には最終発表後に企業の方と名刺交換をして、自身の就職活動につなげた人も多くいます。
こうした多様な実習や企業との連携を通じて得られた最大の収穫は、「自分の強みや興味を実体験の中で確認」できたことです。単に知識やスキルを身につけるだけでなく、現場での試行錯誤や対話を通じて、「自分はどんな仕事に向いているのか」「どんな働き方をしたいのか」といった問いに対して、手応えを持って答えられるようになりました。この大学のカリキュラムは、一人ひとりが自分なりのキャリアの軸を築いていくための実践の場だと感じています。
早期からリアルな社会に触れ、段階的に成長できる仕組みがあるからこそ、卒業後も自信を持って次のステージへ進める。学外での経験に触れながら、自らの将来を言語化し、現実に変えていく。
このプロセスこそが、この大学のカリキュラムの最大の価値だと強く実感しています。
Q. 先生、友人はどんな存在ですか?
私の成長を支えてくれたのは、尊敬できる先生方と、切磋琢磨し合える友人たちの存在です。
先生方は、普段は学生たちに交じって気さくに談笑しています。が、ひとたび教育のスイッチが入ると、学生のためを思って厳しく指導してくれる人が多かったです。その厳しさには常に愛情と論理が伴っていたため、私たち学生も心から信頼し、教えを請うことができました。例えば、評価に不満がある場合、私たちは臆することなく先生に直接話を聞きに行きました。その際も、頭ごなしに否定するのではなく、どの観点から評価してこの点数に至ったのかを、論理的に、そして詳細に説明してくださいました。このような真摯な姿勢は、私たちに「正しく評価されている」という安心感を与え、更なる成長への意欲を掻き立てるものでした。
そして、共に学ぶ友人たちは、かけがえのないライバルであり、最高の仲間。
同じITやAIの道を志す者として、お互いを深くリスペクトし合う関係を築けました。授業や演習で分からない部分があれば協力して解決策を探し、時には友人と共に一つのシステムを協力して作り上げることも。一人では乗り越えられない壁も、仲間と協力することで突破できることを、何度も経験しました。もちろん、勉強ばかりではない。学校外では一緒にご飯に行ったり、遊びに行ったりして、大いにリフレッシュも行い、学生生活を謳歌できました。
先生方の指導と、友人たちとの支え合いがあったからこそ、私の大学生活は実り多く、充実。この環境こそが、私の「やり抜く力」と「人間力」を大きく育んでくれたと確信しています。

就職活動・内定について
Q. 就職活動はどうでしたか?
入学当初から将来の就職を強く意識していたため、早い段階から高いモチベーションで取り組むことができました。その中で特に心強かったのが、キャリアサポートセンターの存在です。
エントリーシートの添削はもちろん、企業ごとの特色を踏まえた面接対策、さらには過去の先輩方が実際に聞かれた質問の共有まで、実践的なサポートが非常に充実していました。形式的な対応ではなく、一人ひとりに寄り添いながら、適切なアドバイスと温かい励ましをくださったことに、何度も背中を押されました。
また、選考の進み具合に応じて頻繁に声をかけてくださり、メンタル面でも支えていただきました。就職活動では思い通りにいかない場面も少なくありませんが、「一人じゃない」と思える環境が、私にとって大きな支えとなりました。
今振り返ると、私の就職活動はキャリアサポートセンターの支援なしには成り立たなかったと言っても過言ではありません。それほどまでに手厚く、そして実践的に寄り添ってくれたことに、心から感謝しています。
Q. 内定につながった自分の強みは何だと思いますか?
「継続力」と「目標達成力」による着実な成長、そして「再現性のある努力」が評価されたと感じています。
大学に入学して初めて本格的にITに触れました。高校ではタイピングやエクセルに少し触れた程度で、プログラミングに関してはまったくの初心者。そんな状態から約3年間、地道に努力を重ね、常に目標を設定し、自分を律して学び続けました。大学生活では、自分から動かなければ何も始まりません。流されてしまえば簡単に時間が過ぎていきます。そんな環境の中で、主体的に学び、確実に成長を積み重ねてきたことが評価されたのだと思っています。
また、「再現性のある努力」の点。たとえ一度だけ良い結果が出ても、それが偶然や一過性のものでは意味がありません。大切なのは、どんな環境や課題に直面しても、自分なりに考え、工夫し、乗り越える力があるかどうかではないでしょうか。私はこれまで、様々な実習や課題において「どう努力し、どう結果を出したか」を一つひとつ言語化し、再現できる形で伝えてきました。そうした姿勢が「この人は入社後も学び続けられる」と判断いただき、内定につながったと感じています。
内定をいただいた瞬間、思わず声をあげて叫んでしまうほど嬉しかったです。これまで積み重ねてきた努力や挑戦が評価されたのだと実感し、大学生活の中で最も喜びを感じた瞬間。初心者から始めたITの道で、ここまで自分を信じてやってきて良かったと、心から実感しました。
ただし、ここで満足して終わってしまっては意味がないとも感じています。内定はゴールではなく、社会人としてのスタート地点。むしろこれからが本当の意味での挑戦の始まりであり、ここで得た自信を支えにしつつも、さらに継続的な努力と成長を重ねていく必要があると思っています。この内定は「結果」であると同時に、「原点」でもある。だからこそ、今後も慢心せず、自分の可能性を広げ続けていきたいです。
Q. 企業でどのようなことに挑戦したいですか? 将来の夢や目標は?
技術力を活かして、企業や社会の根本的な変革を生み出し、より持続可能な未来をつくることに挑戦したいです。
技術革新は、業務効率や利便性を大きく向上させる一方で、人間の仕事が機械に置き換えられ、雇用の不安が生まれるという「負の側面」もあります。例えば、AIやロボットが導入されたホテル現場では、従来のスタッフの仕事が減る一方で、代わりの雇用や再教育の仕組みが十分に整っていないケースも多いと言います。
私は、こうしたギャップを埋めることに挑戦したい。技術が進化すればするほど、人と社会がどうそれを受け止め、活かしていくかが問われる時代。だからこそ、企業が最先端技術を取り入れるだけでなく、それを活用する「人」の成長も支える仕組みづくりが不可欠だと考えています。
アクセンチュアには、デジタル技術を活用した業務改革や新たなビジネスモデルの創出といった「変革の力」があると感じています。私はその現場で、効率化によって生まれた余白を人材育成や新規価値創造につなげる提案を行い、「技術の進化 × 人の可能性」を最大化するようなプロジェクトを推進したいと考えています。そして、自身の将来の夢は「市場価値の高い最強の人間」になること。IT・AIにとどまらず、ビジネス、デザイン、グローバル、マネジメントなど、あらゆる分野に挑戦し、自分の価値を多方面から高めていく。そのためには、あらゆる変化をチャンスに変え、成果に結びつける再現性ある努力と、どんな困難にも折れないグリット(やり抜く力)が必要だと自覚しています。
メッセージ
Q. 入学する皆さんや後輩の皆さんへ伝えたいことは?
みなさん、本気になれていますか?自分という存在に対して一生懸命になれていますか?
大学は自由です。やるかやらないか、挑むか逃げるか、すべて自分次第。だからこそ、「本気」になれる人間かどうかが問われる場所だと思っています。
私はこの大学で、本気で自分に向き合い、自分の可能性を信じて努力し続けてきました。最初は初心者でした。でも、だからこそ自分を信じ、継続し、目標に向かって進んできました。気づけば、それが夢だった企業の内定という形で報われました。でも、それはただの結果です。本当に得たものは、「やればできる」と自分を証明できた経験と、その過程で出会えた仲間、先生、実習先の方々との信頼関係です。大学は、ただ知識を学ぶだけの場所じゃない。人として、社会人として、どう生きていくかを考え抜く場です。
そして本気になるには、遊びも大切です。仲間と笑って、時には羽目を外して、気持ちをリセットすることで、また前を向ける。遊びも学びの一部です。バランスをとりながら、自分らしい大学生活をつくってください。新しい友人との出会い、サークル活動、旅行、アルバイトなど、様々な経験を通して、かけがえのない思い出を作り、人間としての幅を広げてください。本気で学び、本気で遊ぶことで、皆さんの大学生活はより一層輝きを増し、将来の大きな糧となるはずです。
Q. 最後に、本学の特長をひと言(短い言葉)で表すとしたら?
釣り鐘に例えると、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く








